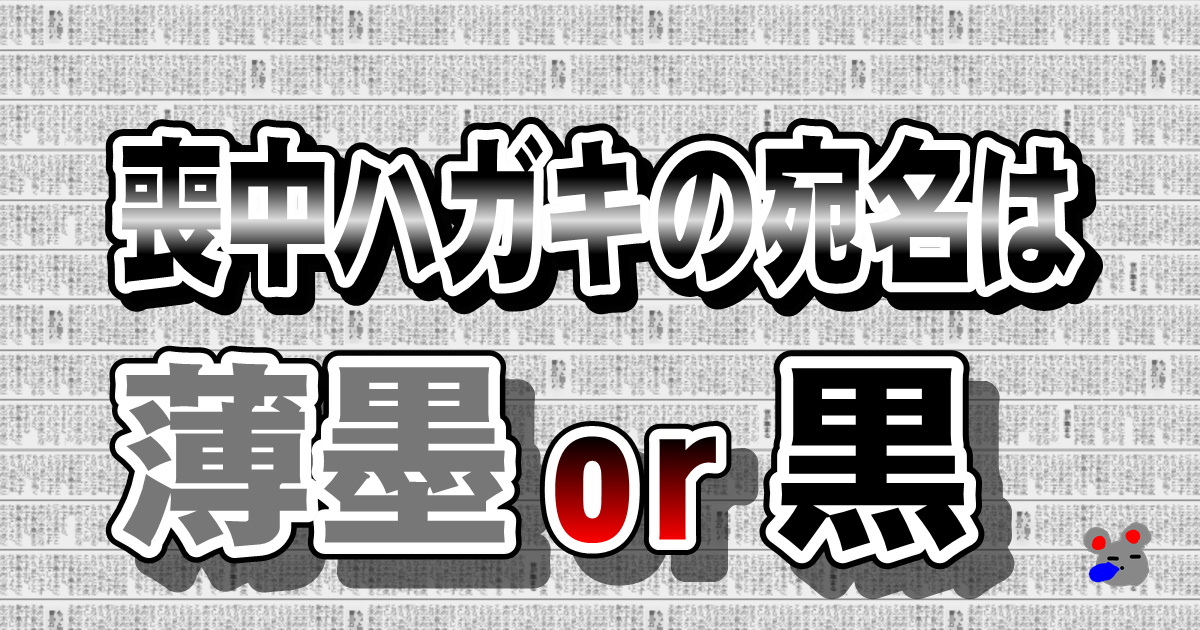弔事は薄墨が基本
前回、母が亡くなったことを知らせるために喪中ハガキを店員さんと一緒に作成しました。
その続編のような形になります。
前回喪中ハガキを100枚作成し、宛名も完璧にチェックし、基本無料の年賀状作成ソフトで宛名印刷をしていたところ、喪中ハガキの宛名は薄い黒(灰色)で書かないと駄目ですよ。
と横やりが飛んできた。
思い返せば6年前の父が亡くなった際も、そのようなことを言われた記憶があり、極力灰色にしたような記憶がある。
しかしだ。
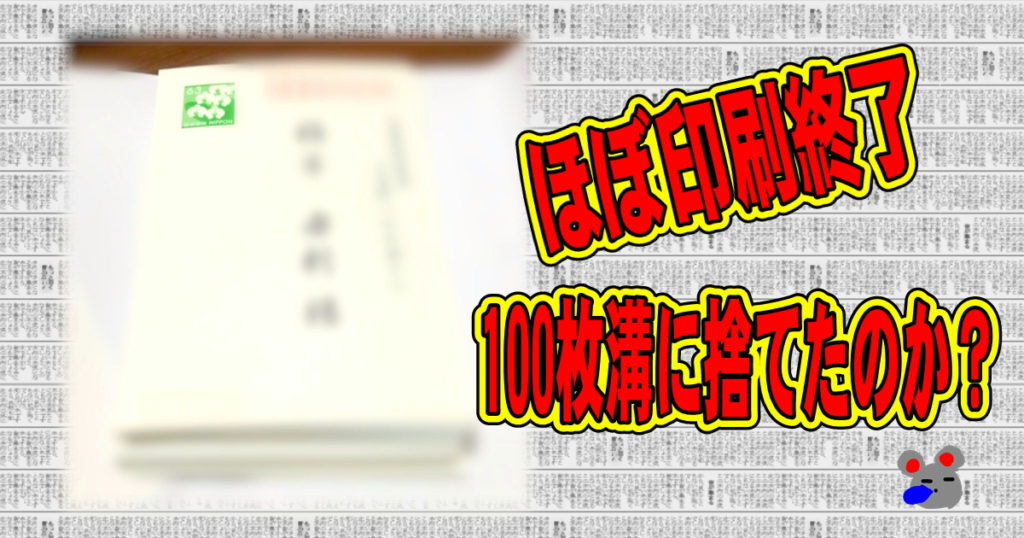
印刷はほぼ完了した。
今更感は半端ない。
そこで宛名は黒では駄目なのか調べてみた。
弔事が薄墨である由来
これは人の死という事が突然の出来事であり、そのことを知って慌てて駆けつけました。
この慌てて駆けつけたには、書道の墨を磨る時間もなく、薄い墨のまま香典を書き、慌てて駆けつけました。
という意味があるらしい。
さらにもう一つ意味があり、真っ黒な墨も涙で薄くなってしまいました。
という意味もあるとの事です。
どちらも時間軸が基本となっており、一つ目は慌てて時間がない、もう一つも悲しみに暮れている真っ最中ということで、故人が亡くなって直ぐの出来事という意味である。
喪中ハガキの宛名は黒
調べつくしてほっとした瞬間でした。
薄墨は故人が亡くなって直ぐの出来事に対する表現方法で用いられたが、喪中ハガキの準備は10月から12月、もう十分に時間があるときに行われる。
たまたま私の母は11月7日ということで慌てましたが、そうでない方もいらっしゃいます。
一般的には十分に時間のある時に作られた喪中ハガキの宛名は黒で、毛筆書体、および筆で書きましょう。が正解。(決してボールペンで書いてはダメです)
そしてここからさらに掘り下げて調べていくと、昔は宛名も薄墨で書かれていたような時があるらしく、実際6年前の父の喪中ハガキも、今回もそのような事を言われてます。
しかし、もう一つの正解があり、宛名の一部である郵便番号は機械で高速に選別されるため、読み取りエラーが起きない黒色でしっかり書くのが郵便マナーとして正解なのです。
それではこの郵便番号の選別する機械とは、郵便区分機と言われています。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
郵便区分機(ゆうびんくぶんき)は光学文字認識(OCR)またはバーコードにより定形郵便物などの郵便番号とあて名住所を読み取り、指定された区分け口に自動的に仕分け、集積する機器。
概要[編集]
OCRでの宛名読み取りおよび、郵便番号読み取り時には、30,000通/時以上。バーコード読み取り時では、40,000通/時以上の処理が可能である。1960年代より東芝や日本電気などが中心となり研究や実験が行われ、初期の段階では価格も高額であるため東京中央郵便局など、全国、主要局で郵便物の取扱量が多い局に限定的に配備されていた。最初の区分機は今ほど多機能ではなく、手書き書体の郵便番号をOCRにより郵便番号を読み取り、全国集配局郵便番号別に区分けするのみであったが、その後ダイレクトメール(宛先のコンピュータの印字化)の増加に対し、宛先郵便番号の読み取り範囲を限定し効率な読み取りを行い、次第に全国の主要局に配備されるようになり、1980年代以降全国的に広がり機能も向上していくこととなる。1998年の郵便番号7桁化と機械自体の価格の低下、地域区分局の整備によって現在のような形態となった。
これを見る限り、郵便区分機が完全に整備されたのは比較的最近の出来事の様なのです。
つまり、薄墨で書かれていても、人が仕訳けしていた時代で有ればかなり薄くても仕訳できた。
という事なのです。
現在は読み取れなければ機械で弾かれ、人が仕訳けするわけですが、行く先々で弾かれ、人が仕訳していては時間も労力もかかり、マナーとして良くないよ。という事なのですね。
郵便番号が7桁になった頃も思い出せますし、郵便区分機の導入も最近という事であれば、宛名も薄墨で書かなくてはいけませんよ。と言われる方がいらっしゃっても間違いありませんよね。
Q & A
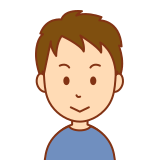
実体験型ブログじゃなくて調べちゃいましたね

100枚やっちまったの実体験になるところでしたので、黒色で正当化できる方法を必死に調べた結果です。